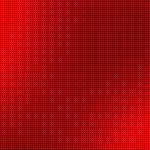あのときの失意の降板・・・。何とも頼りなく、無責任にも見えたものだったのに・・・。
今年になってからだろうか、ほぼ毎日のように聞くことになった「アベノミックス」。テレビのニュースやインターネット、新聞、雑誌、週刊誌・・・。
あの時と同じ人物か、と見紛うほどに自信に満ちあふれた表情、全くの別人かとすらみえたものだ。
「アベノミックス」、内容は異なるが実は、あの頃からも言われていたもの。しかし、今回は期待を込めて様々な場面で語られており、我が国の明日に希望を託すキーワードになっているようだ。
「給料は上がりましたか?」「生活は楽になりましたか・・・・?」
そう尋ねてまわる記者やインタビュアーにもいささかあきれることだが・・・。
「金融政策」と「財政政策」、「成長戦略」という強い日本を取り戻すのだという「3本の矢」は順次放されたばかりなのに・・・。すぐに効果があるという単純なはなしではないだろう。
安部氏は、健康上の理由もあって不本意ながら総理大臣を退陣せざるを得なかった。その後の数年間は自らの復活に賭けた政策研究の日々を送っていたのだといわれている。多分、この時、多くの人や信頼するブレーンとの交流があり、ある種の確信とこれ以上に失うものはないのだという不退転の覚悟をも持つことになったのだと思われる。不名誉な退陣であったのだろう・・・。挫折というまさに政治家としては致命的ともいえる経験をしたことが契機であったのだろう。しかし、人は失敗し、挫折を経験することも案外大切なことで、それまでの「縮小均衡の分配政策」から、「成長による富の創出」へと大きく転換させ、経済界や庶民の心をとらえることになった。20余年も続いた出口の見えない不況感を払拭して欲しいという期待こたえる大胆な決断が、「見えるもの」になっていったということもある。
その強力なパートナーともなる日銀総裁も意中の人物を引き出し、3本の矢はより強固になり、確かに的を射はじめたようにみえる。
さらに、海外市場の拡大につながる円安が一気に進み、世界マネーが我が国を窺い株高をもたらしている。
歯ぎしりをする思いだった産業競争力も、いまは強力に推進する世界戦略が実行されようとしている。
衆知を集め景気浮揚のために「よい」と思われるものは何でもやるという決断が、 即行動という、我が国としては常識を突き抜けるリズムが生まれている。
変化を生む行動にはリスクをともなうこともあるのだろうが、それらの挑戦がなければ、なにも変わらないことになる。
・・・・・
最新の科学技術の進化は、なにか世界の均質化のスピードを早めているように、20年余のブランクを経て、どうやら国をあげての戦う姿勢を整えつつあるようだ。世界的な不況感の中で、異常なほどの円高が輸出の足を引っ張り、我が国を牽引していた車や家電、機械などの輸出型企業の苦戦が強いられ、ことさらに我が国の存在感が世界の市場から忘れ去られ、デザインの存在や質ですらも否定されていたのだから・・・。当然ながらマスマーケットを構成する途上国を市場とすれば、韓国や中国企業との低価格競争となり「高ければ売れない」という負け組の烙印。最近は、輸出産業全体の活力も失わせているのだというニュースが繰り返され、コメンティターの解説も「デザイン自体も後発企業に後れをとっており、我が国の製品は「品質」で勝負するしかないでしょう」という不愉快なもの・・・。
いまこの時に、この「円安」傾向は、デザインとしても需要を創造しうる取りくみが可能になるはずだ。成熟した市場経済の中で、同じことを繰り返しているだけでは成長はなく、結局は値下げ競争に陥るだけであったという教訓がある。
デザイン理論教育の浸透・・・・、
パソコンを軸にした技術や視覚的な情報・知識の「教え」「習う」というシステムには平準化、共有化はあるものの発想の独自性を希薄なものにし、様々な与条件を課せられることもあって独自に深く思考し発想する時間が極めて少ないことが気になる。また、デザイナーが最も能力を発揮せねばならないだろう「形」や「色」の部分についても、よりよいものとしてのオリジナリテイを見出し、リ・ファインを繰り返すことの訓練が少ないのではと思われることだ。強く影響する仕組みが前提となりすぎて個性・独自性を失っており、それらを超えて発想するという意欲を希薄なものにしている。
若い自らの感性、時間を忘れてギリギリに追いこむ形態開発の修練を試みることも大切なのだと考えている。
まず理論を、と考えがちな高等教育も真の創作理論は、じつはデザインを極める中にこそ見出すものでもあると考えるからだ。
国内のユーザーはともかく、環境が異なり、多様な価値観を持ったユーザーからみればデザインの革新性としての欲望は明らかに異なるものだろう。その変化がまず見えるものが「形」と「色」なのだから、無機的な表情だけでは受け入れられず、「魅力に欠ける」とすらみられているのではないか、と思われることだ。
経験の少ないデザイナーにとっては「学んだ」という思いだけの意識をもってルーチンワークとしての「ものづくり」であれば、なおさらのことだろう。
ユーザーとなるべき、それらの国々にある欲求を必要条件として理解できる感性をもっこと、その発想と開発力が重要。これはこれまでも繰りかえしていることだが、もちろん、製品のモノづくりにある思考、生産性をフレキシブルに維持することを心せねばならない。
強み!日本らしさとは、基本的な「品質」を確りもつことであり、それが斬新で魅力的なモノの表情を持ち、オリジナリテイであることも条件だろう。
これまでに培ってきた日本のモノの品質、その中にデザインも含まれているはずなのだが一般的な理解されていないようだ。
適切な機能であり、美しいモノを所有する喜びと誇りに応えるデザイン。
何よりも、デザイナーが個人として手探る中で、常に新鮮な眼差しを生活環境に向け、とらえることに自らの全身で感じ取って欲しいことだ。
「変える」、「新しくする」という問題意識とアンテナは、常に研ぎ澄まし自らの可能性として「魅せる形態」が共感されるものでもあろう。
意識ある多くの企業が参戦し競い合うことになるが、その中で戦う姿勢、強く生きる姿勢こそがいまデザインにも求められている。
常識を突きぬけたアイデアや新たな形や色の可能性を極める必要を感じてもいる。
ただ、何よりも企業の意思決定権を持つリーダーの先験的な見識にかかわる問題でもあり、それらの斬新な提案も理解し、評価・決断する力に依存せねばならないことだろう。
(2013/5・2 記)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモ:コラム
・20世紀の高級車から大衆車までアピール競争
高級車市場では、以前から各社ともフロントに共通のデザインを採用していた。独BMWの「キドニーグリル」、独ダイムラーの「スリーポインテッドスター」、独アウディの「シングルフレームグリル」、最近ではトヨタの高級車ブランド、レクサスの「スピンドルグリル」などがある。
共通のデザインは、どのブランドの高級車であるかをひと目で周囲に知らしめるアイテムとして、消費者の心理をくすぐってきた。ダイムラーがベンツ車に搭載するスリーポインテッドスターを大きくするなど、最近は高級車ブランドによるアピール合戦がますます激しくなっている。
その動きは、これまでどちらかというとデザインより機能性が重視されてきた大衆車の分野にも波及しつつある。例えば独フォルクスワーゲン(VW)のクルマは正面中央のエンブレムから左右一直線に伸びるフロントグリルが、韓国・現代自動車は六角形のフロントグリルが特徴だ。韓国・現代自動車の「エラントラ」。六角形のフロントグリルが特徴だ。こうしたフロントデザインの共通化は、シェアの低い地域で自社ブランドの存在感を示すのに有効である。町中を走っている台数が少なくても、車種ごとにフロントデザインが似ていれば、消費者に「よく見かけるブランドだ」との印象を与えることができ、認知度は高まる。なかでも成功例と言われるのが現代自だ。2011年の世界販売台数は660万台に上り、ホンダや米フォード・モーターを抑えて5位となった。現代自の躍進を支えた米中市場で、六角形のフロントグリルが果たした役割は大きい。2011年の世界販売シェアが3位(795万台)のトヨタ自動車の地位も、安泰とは言えなくなってきた。特にトヨタ自動車にとってテコ入れが必要なのが欧州市場だ。5割近くがトヨタ車という日本国内と違って、欧州市場のシェアは4%にとどまる。オーリスは低迷する欧州市場の開拓に主眼を置いた戦略車だ。新型オーリスを皮切りに、次々とキーンルックのクルマを出すことで、シェアの低い欧州市場で「トヨタ車、ここにあり」を印象づける。
・デザイン統一に再び取り組むソニー
かつてはソニーが製品デザインを統一していた。
1960年代に黒と銀を基調とした「ブラック&シルバー」を打ち出し、一見してソニー製品だと分かるようにした。そして「ポータブルラジオ」や「トリニトロン」などの大ヒットにつなげた。しかし、時間の経過とともに、いつしか製品ごとのデザインはバラバラになってしまった。製品デザインと企業イメージが結びつかなくなり、テレビや携帯型音楽プレーヤーなどの分野でシェアを落とす一因になった。今、アップルの成功に触発され、今年4月にソニー社長に就任した平井一夫氏は「統合された顧客体験の提供」をキーワードに、再びデザインの統一を急ぐ。
一方、自動車業界では現代自の影響もあり、トヨタ自動車がデザイン統一を急ぐ。日本を代表する2社のメーカーが、消費者へのアピール力を高めるために同じ解にたどり着いた。それは決して偶然ではなさそうだ。デザインの統一という大きな潮流が、あらゆる分野に及び始めた。
――吉野次郎氏 著者プロフィール
日経ビジネス記者。1期生として慶応義塾大学環境情報学部を卒業。1996年に日経BPに入社し、通信業界の専門誌「日経コミュニケーション」で2001年までNTTと新電電の競争や業界再編成を取材。2007年まで通信と放送の専門誌「日経ニューメディア」で、通信と放送の融合やデジタル化をテーマに放送業界を取材。現在は「日経ビジネス」で電機やIT(情報技術)業界をカバーする。(日経BP)