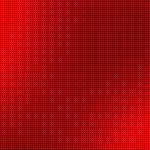のちに印象派の父とも呼ばれ、19世紀フランスを代表する画家エドウアール・マネ(1832-1883)は、創作の糧を得ようとスペインに旅した。
王室の収集品が並ぶ世界屈指の美の殿堂といわれるプラド美術館を訪れパリのルーブルでも観ていたスペイン絵画、その16世紀以降の傑作がならび展示されていることにも感動していた。とくに西洋美術史上最大の画家のひとりでもあるデイエゴ・ベラスケスの作品、なかでも「道化師パプリロス」には強く感ずるものが、それが何かを考え学んでもいた。黒い衣装をまとった道化師が画面の中央に立つ、その姿を灰色の空間に浮き上がらせており、わずかに足下におとす影が大地を感じさせているのだ。色彩の単純化とあわせ、これまでの絵画史上にはない時代を先取りした斬新な実験を繰り返していた。この絵に触発されたのが、黒シャツに赤いズボン、右肩から左へ流した白いたすき姿で笛を吹いている少年軍楽隊の「笛吹く少年」の絵だった。マネは私淑するベラスケスを「画家の中の画家」と高く称えてもいたのだ。
意外に思えたのだが、あのピカソもまた、ベラスケスをリスペクトしていたということだ。17世紀のスペイン王室の人々を描いた、「ラス・メニーナス」は、気品をたたえた幼い王女マルガリータとその世話係だろう侍女や従者、その足元の犬・・・。奥の鏡にはそれらを眺めている国王夫妻の姿も。なによりも興味深いのは絵筆とパレットを手にした画家・ベラスケス自身がキヤンバスの前面にキャンバスを立てて描いている姿までもが絵の中に描き込まれている。その視線は、この絵を見るであろう人々に向けられている。好奇心旺盛なピカソを捉えるには十分だろう。一見平明にみえるが眺めるほどに謎めいてくる絵の魅力に心奪われてもいた。芸術家としての絶大な名声を得ていたピカソも既に76歳、いまの関心ごとは「絵を描くこととは?」、「描くことの本質とは?」、「画家とは何か?」と言うことにも関心があった。画家ベラスケスの絵には、幼いころから目にし、特に10代の頃にはひたすら「真似ぶ」絵でもあったろう。が、20代からはそれらを否定し、挑戦し、乗り越えねばならないライバルにも。尊敬するベラスケスは偉大な画家であり、その発想力に、モチーフの画面構成にも強く触発され興味を持ってもいたのだろう。その絵を超えることが次代を背負うものの宿命でもあろうとの考えは、「ラス・メニーナス」の人物や描かれているもの全てを取り入れた絵、空間構成に挑戦したいと言うことでもある。岡本太郎がピカソに触発され、アカデミックなものへの挑戦者でもあるピカソをライバルとしてとらえてもいたことに通じる・・・。自分の眼で捉えた「形」とその「空間構成」に挑戦する!自分の表現の限界を求める挑戦でもあったのでは・・・。晩年のピカソの大きな関心事でもあった。そのための探究は、ベラスケスの「ラス・メニーナス」をテーマに挑戦した連作、ピカソの「ラス・メニーナス」は58枚にも・・・。「真似るためには元の対象を完全に消化したうえで全く別なものとして表現する」とピカソ。
(2018/6・3記)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモ:
●芸術の創作において「真似も模倣も盗作もコピーも影響も本質的には皆一緒だ」と。「無」からはなにも生まれないし、生まないものだ。オリジナル100%の作品は、ない!「何も真似したくない人には、何も作れない」と画家サルバドール・ダリ・・・。兎に角、その最右翼にいるのがピカソ?社会通念、倫理上の問題として功罪が問われたりのするのだろうに・・・。
・真似るためには元の対象を完全に消化したうえで全く別なものとして表現する。
・刺激を与えてくれる尊敬できるライバルを創り、その存在そのものからも真似ぶ
・デッサンによって対象の本質を正確に捉える能力を磨く・・・・
●「すぐれた芸術家は真似る!偉大な芸術家は盗む!」と。ピカソの言葉だと言われている。が、多かれ少なかれ芸術家、美術、音楽家などもそのような言葉を残しているし、あの、ステイブ・ジョブスもピカソの言葉だとして引用しっていた。
●『プラド美術館展』―静かな絵画革命・宮廷画家ベラスケスの実験―放映にゲストとして登場していた漫画家荒木飛呂彦氏は1987年から連載の「『ジョジョの奇妙な冒険』にベラスケスの『王太子バルタサール・カロス騎馬像』その技法を真似て描いているんです」と、テレ笑をして・・・。
●ピカソは宮廷画家ベラスケスの動機や気分を十分に読み取って再現するという模写ではなく、58通りの王女の形を「自分がみたように」変えて置き換えてみるという試みであり、侍女たちもそれぞれに58名の形・・・。構成も58通りの連作に挑んだと言うことになる。勿論1枚目(No1-1957年76歳)から始めるわけだが1枚、10枚、20枚・・・58枚ものオリジナル化に挑戦すると言うことになる。IDの発想量が問題になるように、極めてハードで忍耐を要する試みでもあるに違いない。凄い!
●後期印象派の画家ポール・ゴーガン(1848-1903)――自然を模倣(写実的表現を)せず、己の内に感じるままに、ある種の抽象性を以て描く「説教の後の幻影」心象風景。その試みに重要なのは絵のテーマを色で表現したこと。その色も眼で普通に見える色ではなく自分の心の色、全く新しいコンセプトだった。ゴーギャンは赤を感じ、同じパルドン祭のテーマでもエミール・ベルナール(1868-1941著述・画家)は黄緑を感じたのだと。画家の個性は色、構成など見たままを描く印象派とは違う感じた心の色で表現する新しい芸術なのだと。
その絵を教会に寄付したが、受け取りを拒否されたのだと言う。「新しすぎた!」「大胆過ぎた!」と。2人の次作は「黄色いキリスト」(1889)いろんな文化を吸収し、それを自分の中で昇華させ、新たな芸術へ発展させること、芸術は常に変化する。そのための旅なのだと。